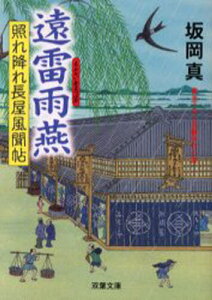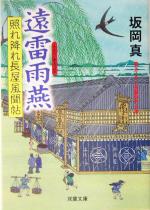雷雨 特異性ある創造と貢献
★関東地方 神奈川県のパワースポット★
~過去のブログと統合しています~
つづいては~
私が大好きな神社。![]()
![]()
都心からも近い場所にあります
師岡熊野神社 へまいりましょ~~
ご祭神
伊邪那美尊、事解之男命、速玉之男命
住所
神奈川県横浜市港北区師岡町1137
行き方
東急東横線大倉山駅→徒歩8分
大倉山駅から商店街をぬけて
神社に近づくと、少し自然が増えてきた・・・?!![]()
わぁあぁあぁ~っ
ここっ、ここっ!!
ここにくると空気が変わるよ~。![]()
柔らかな風が届いてくるような
清らかな優しい空気。
・・・・![]()
![]()
そしてね、ここにきたら~左側に注目。
水の神様が祀られていま~す。
だから、弁財天様に挨拶したあとは
忘れちゃダメダメ。(笑)
この池に向かってご挨拶~で~す。
はぁああぁぁ・・・。![]()
くるくる~ふわぁぁぁ~~~
水の神様の気で全身が洗われる~。
水滴が落ちた水の模様のみたいに渦巻く気。
軽やかな風が膨らみ
体が清められ、気持ちいい~~。
ふぅ~
弁天社の後ろのベンチで一休み。
おばあちゃん気分。(笑)
このベンチでボーッとしているとね
不思議と頭がホワホワ~って軽くなってくるの~。うふふ。
そうそうっ!
この師岡熊野神社のすぐそばには
杉山神社があって
お散歩できるコースがあるのよ~~。![]()
このあたりは
自然がまだまだたくさん残っていて
パワースポットもいっぱいで~す。![]()
さっ、道路をほさんで反対側が
関東随一大霊験所 師岡熊野神社ですっ
�家光公、寛文5年家綱公より御朱印地を載いたのを始め、代々の将軍家の崇敬きわめて篤く、神社への御朱印は幕末まで続けられた。
ちなみに、社紋になっている八咫烏は
熊野大神のお使いである神使。
夜明けを呼ぶ鳥、太陽を招く鳥ともいわれ
人生に迷い闇に覆われ悩むときも、明るい希望へ導く霊鳥
足の守護神、人生の導きの神と信仰されているそうです。![]()
師岡熊野権現宮といっていたんだね~。![]()
師岡熊野神社の筒粥
社伝によれば、この行事は村上天皇の天暦3年以来、
神社石段の右側に鎮座している、表谷戸上講中の稲荷社。
地神塔と祠、素朴なきつねさまがいま~す。![]()
![]()
はぁ
はぁ
あっ、今日は軽い~私の足。![]()
この階段ね不思議なの。
登るとき、軽く感じるときと重く感じるときがある。
自分の体のエネルギーが軽いときは
階段がつらく感じないんだけど
自分の体のエネルギーが重いときは
かなりしんどいんだよぉ。![]()
はぁぁぁあ・・・・![]()
最近師岡熊野神社は
手水舎も境内の雰囲気も
いろいろ新しく生まれ変わったの~。
開いた空間で明るい印象の神社。
綺麗になったというか
こざっぱりした感じ。
くるくる~くるくる~~~
温和な空気、清らかな空気が流れ
氏神様らしい雰囲気よ~。
ふひぃ~
体も心も、元の気に戻って
心の安定となりそうな力。
いーきかーえるぅぅーーー。![]()
でもね・・・もっといいところが・・・
うひょぉぉお~~~
こっちっこっち!
エネルギーが一段と高くなるよ~~。
やっほっほ~~。![]()
な~~んと厳かな雰囲気でしょう・・・。![]()
この森・・・すごい力なんだよぉ~
ぐる~~~ぐる~~~してるぅぅぅぅ~~~~~![]()
![]()
ここですっ!
ここですっ!
のの池さまぁぁぁぁ~~~~。![]()
のの池
当神社草創の地である。
この池の水は禅定水と呼ばれ、
どんな干天でも涸れることがなく
大雨でも水があふれることもないといわれています。
南北朝期の落雷による火災で、社殿が焼失した時
神宝、神体等をこの池に投げ入れ
焼失を免れたと伝わっています。
今は池の周りが舗装されているけれど
以前は土のままだったの。
それでも、不思議とず~っと枯れることがなかったよ~。![]()
はぁぁぁあぁ・・・・![]()
くるくる~ビリビリビリ~
木の根元にたまった水の方からは
女神さまのような、ふわりとした気・・・。
しっかりパワーがあるけれど
心に慈悲深いやさしいエネルギーを届けてくださる・・・。
合わせている手のひらが
ぽかぽかあったくなって・・・心も穏やか。
体が重たくなっているときも
こちらの神様に挨拶すると、
�
��わぁ~って体を軽~く戻してくださったりするんだ~。
私は、と~ってもお世話になっている神様・・・
いつもありがとうございまーす。
![]()
その隣には・・・
昔は、祠が並んでいる感じだったんだけど
ピンピカピン!新しく生まれ変わったお社が並んでまーす。![]()
★天満社 菅原道真公
社号は天満大自在天神。『天神』『天神さま』ともよばれている。
祭神の生前の名前から菅原神社
天神を祀ることから天神社などとなっていることもある。
道真公の怨霊信仰から発し、雷雨を招く農耕神へと転化し
近代以降は祭神の徳を称えて学問の神として崇められている。
現在の熊野神社市民の森内、天神山広場内に祀られていた社を
明治四十年に現在地に移設したものである。
男性的なパワーで
思考と整えてくださる感じがする~。
★社御神 石神
由緒不詳。長野県の諏訪信仰を源流とする農耕神であり
食を下さる杓子奉納を象徴とするミシャグジ信仰は
東日本の広域に渡って分布しており
当初は主に石や樹木を依代とする神であったとされる。
近世からは、その語呂から俗信として癪の神、咳の神などへも
転化している。
ドシリと地に降りていく気で
石の重みや忍耐?強さ、安定をイメージする神様~。
★山王社 大山咩神 大物主神
山王社は山王信仰に基づいて、日吉大社より
勧請を受けた神社で日枝神社とも称して日本全国に
約三十八社ある。神仏習合期には山王と称され
今日でも山王さんの愛称で親しまれている。
猿を神使とする。当社は師岡の表谷戸上の講中にて
祀っていたものを何時の頃か現在地に移設したものである。
穏やかなエネルギーで、頂上をイメ―ジする
気持ちいいエネルギー。
★白山社 菊理媛大神
白山は、富士、箱根とならび『日本三名山』のひとつに
数えられる秀麗な峰である。白山から流れ出る豊富な水は
北陸から東海地域まで豊かな恵みをもたらしている。
このため、古代より白山は『命をつなぐ親神様』として
崇められていた。師岡仲谷戸にあった社を
明治四十年に現在地に移設したものである。
はぁぁ~。透明感のあるエネルギー。ホッ。
そのほかにもたくさん神様がいらっしゃるよ~。
稲荷大神 宇迦之御魂神
御嶽社 大己貴命 少彦名命
道祖神 猿田彦神
浅間大神 木花咲耶姫命
水神宮 弥都波能売神
熊野神社の伝説の池の中で
唯一境内地を離れ、昭和五十年代に埋め立てられて
公園(大曾根第二公園)となっている
『ちの池』に祀られていた水神様を当社に移設したものである。
こちらには、仏像がならんでいま~す。![]()
馬頭観音像
江戸時代に西国三十三ケ所・坂東三十三ケ所・
秩父三十四ヶ所を巡礼してきた人が
満願を記念して建てたとされる。
本人の記念ということではなく、自ら得た功徳を
他者にも施すという意味もある。
師岡表谷戸の下郷にあったもの。
青面金剛像
六十日に一度回ってくる庚申の日に人の身体の中にいる
さんしの虫をおさえる力をもった金剛童子で
青い顔で憤怒の形相をしている。
三猿を従者としている。
地神塔
春分、秋分に最も近い『戌の日』を社日といい
前夜に講の人々が当番の家に集まり
『堅牢地神』の掛け軸をかけて、
地神の日待を行い、翌日の社日は農耕作業を休んだ。
社日は、田の神と山の神が交代する日と考えられたため
その年の稲の豊作を願い、農業に関係の深い土地神様を祀る
このような行事が行われるようになった。
そ~してそしてっ
忘れちゃいけないのが、こちら。![]()
神明社 天照皇大神
天照皇大神を主祭神とし、我が国の総氏神として仰ぐ
伊勢神宮内宮を総本社とする神社である。
皇大神社、天祖神社などともいい、通称として
お伊勢さんと呼ばれることが多い。
元々師岡南谷戸にあったものを、明治四十年に
当社鳥居脇に移転。昭和三十年代に現在地に
移設したものである。
ぐるぐる~ぐるぐる~
かなりワイルドな力のある天照大神様だよ~。
パワーが強い~強い~。![]()
・・・ってわけで
もうお腹いっぱいになりそうですが
ここからも、大事。(笑)
この山をのぼりますぞぉ~。
ヘイホッ
ヘイホッ
風が吹き、木々がさわぐ。
落ち葉の乾いた音と
鳥のなき声。
たまに聞こえる飛行機の低い音以外
ここには自然の生きている音しかほぼしない。
一気にどこにきたの?という感じだよ~。(笑)
そういえば・・・
以前きたとき、一度だけ。
この山の上が
真っ白な光に包まれていたことがあってね・・・
あまりにもびっくりして
目をぱちくりぱちくり。
本当に雪のように真っ白な世界だったの~。![]()
(でも季節は秋)
まるで天界から神様そのものがおりてきたような?
UFOでも降りてきた?というくらい
光 光 光。
ひぇえぇぇぇぇ~~~![]()
![]()
ものすごい上昇するエネルギーで、
口あんぐり、しばらく動けなかった。
何もかも、真っ白な光に飲み込まれていく感じで・・・
これが、神様・・・なんだって・・・感じて・・・。
今、思い出しても夢の中のような感覚で
うまく伝えられない。
この神社に、何度来ているかわからないけれど
その一回だけ・・・。
でもね、ふつうの時でも
この山に入ると気の力がグッとあがるの。
こういう聖地って、
都心にはあるようでなかなかない。
特別な聖地だと感じるんだ~![]()
やっほっほ~~~![]()
5分ものぼらないうちに
権現山広場にとうちゃく~~っっ![]()
師岡貝塚
鶴見川中流の右岸丘陵上にあり、北西へ張出す半島状大地の基部から北東に分岐した舌状台地南半部に所在し、標高は約43メートルです。貝塚の規模は東西約20メートル、南北約15メートル以上と推測され、ハイガイが主体をしめ、他にハマグリ、アサリ、シオフキ、オキシジミ、アカニシなどからなる海水性のものから構成されています。
本貝塚は縄文海進によって形成された古鶴見湾岸に分布する縄文時代前期貝塚郡のうちで保存状態が良好な貝塚として、さらに市域での類例の少ない中期前半の貝塚として貴重です。
・・・ってことは
この辺り海だったんだねぇ~っ
えええっっ!?
か・・・貝?!
木々のカルシウムのため??
いやぁ~まさかまさか
貝塚の貝じゃないですものねぇ?!
よくみてみると
貝のかけららしきものが
ところどころ散らばってる。
えぇ~どっちどっち???
はああぁぁぁ・・・・![]()
ぐるぐる~くるくる~
ここここ、左側。
私がだーいすきなところ。![]()
柔らかなあたたかい気があってね
きもちいいの~。
自然界の妖精のような気で
とても優しくて、包容力があって、癒される~。
でも、細い木があるだけだけど。(笑)
こういう特別磁場があるところって
きっと昔は何かあったんだろうなって思う。
今は木の幹がおれてしまったけど
そこも、どなたかがお祈りしているようなエネルギーが残っていたから
この場所は、広場として生かされているけど
実はパワースポットなんだ。![]()
だから、ここにきたらゆ~くりの~んびり・・・。![]()
景色を眺めて・・・
ベンチでごろ~ん。
![]()
空をみあげていたら
木々がはなれたりくっついたり
スローモーションで
ワサ~ワサ~とゆれうごいている。
眺めていると木々の動きが
海の波みたいにみえてくる。
自然って空も海も木も動きがにているんだね。![]()
ふぅぅ・・・![]()
・・・というわけで
せっかくきたなら
この山まで上がるのがおすすめです~。
きっと、自然界の栄養を
たくさん与えてくれますよ~。
都内や神奈川に住んでいる人は
近いのでぜひきてくださいね~。(笑)![]()
![]()
マスコミが絶対に書かない雷雨の真実

雷雨 関連ツイート
2人の時間が再び交わる場面をイメージ🌱
緑はタカオ君、ピンクはユキノさん。
冷たい強炭酸は激しい雷雨か…⚡️
#言の葉の庭
#言の葉の庭オフ会 https://t.co/uyDtQ5cVeH
2人の時間が再び交わる場面をイメージ🌱
緑はタカオ君、ピンクはユキノさん。
冷たい強炭酸は激しい雷雨か…⚡️
#言の葉の庭
#言の葉の庭オフ会 https://t.co/uyDtQ5cVeH